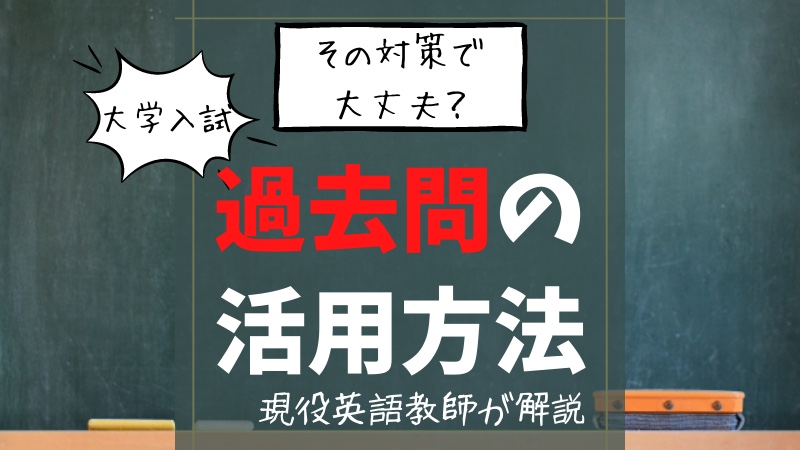大学入試において志望校に合格するため過去問の活用は必須。
受験する大学の過去問を解いて、傾向と対策を掴むことが合格につながります。


実際に、過去問ってどうやって活用したらいいのですか?ただ問題を解くだけ?
過去問を解くことはもちろん大切だけど、問題を解いて解説を読むだけだと活用できてるとは言えないし、もったいない。


大学入試のために、過去問を解くことはもちろん大切ですが、有効に活用ができていない人が多く、とても残念です。
この記事でわかること
- 過去問の3つの活用方法
- 過去問を利用した勉強方法
この記事では、過去問を徹底的に活用して、合格へと近づくための方法を現役の高校教師の立場から解説していきます。
動画でも解説していますので、合わせてご覧ください。
大学入試 過去問の3つの活用方法


まずは、過去問の3つの活用方法を解説します。
過去問を使って問題を解いて終わりではいけません。しっかり活用していきましょう。


活用方法ですか?問題を解いて、解説読む以外に使い道ありますか?
もっともっと過去問を有効的に使うためのポイントを押さえておくことが大切だ。これから説明する3つのことをまずは実践してみよう。


過去問の活用方法①具体的な点数の目標を決める
過去問を有効活用する最初のステップは、合格最低点や合格平均点から具体的な目標点を知ること。


目標点って大体8割くらい取れたら大丈夫なんじゃないですか?
もちろん、試験で8割、9割得点できたら間違いなく合格だけど、私大や国公立の個別試験でそんな圧倒的な点数は取りにくい。というか、個別試験で8割が目標というのは現実的ではない。


勉強する上で大切なのは目標設定です。そのために具体的な目標点を知っておくことが重要ですね。
以下が一般的に合格ラインと言われている得点率になります。
一般的な合格ライン
- 国公立大学個別試験:5〜6割
- 中堅私立大学:6割
- 難関私立大学:7割
赤本などの過去問題集を手にして過去問を解く際に、もう少し踏み込んで、合格最低点や合学者平均点を調べておくと、志望大学合格のために必要な得点が明確になります。
いわゆる赤本などの過去問題集には合格最低点や合格平均点が掲載されています。さらに大学によってはHPで公開しているところもあります。
私の母校の過去のデータを例にして考えてみます。以下のデータはHP上に公開されていました。


国公立大学の場合は、「総合点」、「大学共通テスト」、「個別学力検査等」の3つが公開されています。
基本的には、「合格者平均点」を目指していくのがセオリーになります。
例えば、私の出身学部の文学部であれば、個別試験が800点満点(400点2教科)で418点(合格者平均点)が目指す得点になります。


5割ちょいが目標だと考えると少し気が楽ですね。
あれ?文学部の「合格者最低点」は332点だから、332点取ればいいんじゃないですか?
国公立大学は「大学入学共通テスト」の点数を入れた総合点で判定されるので、332点で合格した人は、「共通テストでそこそこ点数を取っていた」ということになる。つまり「合格者最低点」を目標にするのは少し怖いよね。


国公立大学に限らず「合格平均点」を意識して目標得点を設定していけば間違いがないでしょう。
ほとんどの国公立大学が過去の入試のデーターをHPに掲載していますので、自分の志望大学のHPをチェックしておきましょう。
また、旺文社の『大学受験パスナビ』サイトでは、入試データをチェックできるのでおすすめです。


このように、ただ漫然と問題に取り掛かるのではなくて、「英語で〇〇点、国語で〇〇点、数学で〇〇点」というように、自分の目標点を明確にすることが、過去問活用の第一歩になります。
活用方法② 問題の形式から傾向を押さえる
過去問活用の2つ目は、問題を解く中で設問パターンを押さえておく、つまり傾向を知ること。
実際に過去問に取り組む際には次の2点に留意しましょう。
- 最低でも5年分は解く
- 古い年度から新しい年度へ順番に解く
5年間分問題を解くと、その大学の問題形式が見えてきます。
例えば、英語であれば、「毎年、長文の中に語句整序(並び替え)や下線部和訳が出てくる」など、その大学の設問の一定の形式が見えてきます。
まったく同じ問題は出ないかもしれないけど、同じポイントを問う問題は出る!


もちろん、多少の形式は変わるかもしれないけど、そこまでガラッと変わることはほとんどありません。
古いもの(2017年度入試)から5年分の問題を解くことで多少の変化にも対応できるようになる。
問題の形式はもちろん、出題者の狙いのようなものが、見えてきます。
活用方法③ 問いの難易度から戦略を立てる
活用方法3つ目は、合格への戦略を立てることです。
別の言い方をすると、問題の難易度を知って、合格点への最短コースを取りましょう。


ちょっと意味が分からないです。
簡単に言うと、「点数を取れる問題と取れない問題を見極めよう」ということだね。


入試問題の設問はすべてが同じ難易度ではないし、すべてが難問という入試問題はありません。
もし、すべてが難問と感じるのであれば、それは受験する大学と自分の学力のミスマッチです。残念ながら・・・。
同じ入試問題の中にも、簡単な問題(自分が得意な問題)から、難しい問題(自分が苦手な問題)と難易度が違います。例えば、下線部和訳が他の問題と比べて著しく難しい場合もあるし、逆に英作文が簡単な場合もあります。
難しい問題はあえて捨てて、易しい問題や標準的な問題を確実に解いて、点数を稼ぐことが大切になります。難しい問題でとった点数も、簡単な問題でとった点数も同じです。
悪い言い方をすれば、ずる賢く立ち回ることが必要。


合格への目標点は決まっているので、難しい問題に時間を割くより、確実に点数が取れる問題を優先的に対策した方がいい。


確かに。苦手な問題や難しい問題はササっと流して、確実に解けそうな問題に集中した方が効率が良さそうですね。
もちろん理想はすべての問題に取り組んで正解することだけど、なかなか理想通りにはいかないのが本番の入試です。
どの問題に集中して、どの問題を流すか、という戦略を練っておくことが実際の入試ではとても大切。
過去問を解いて、問題の難易度を分析し、どうやって合格点を取るか、という戦略を立てることが可能になります。
ここまでは、過去問の3つの活用方法を解説してきました。
過去問の活用方法まとめ
- 具体的な目標点を決める
- 問題の傾向や形式を知る
- 確実に得点できる問題や捨てる問題など優先順位を決める
ただ単に問題を解いて解説を読むだけでなく、以上3つのポイントを押さえることが、志望大学合格への近道になります。
大学入試 過去問の3つの勉強方法
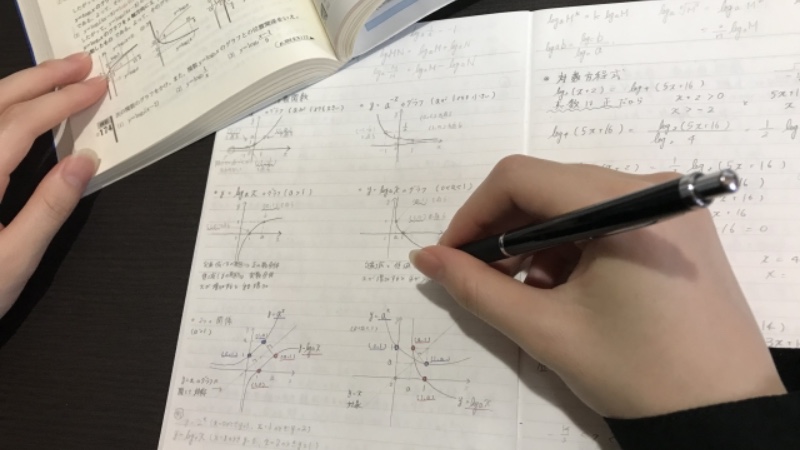
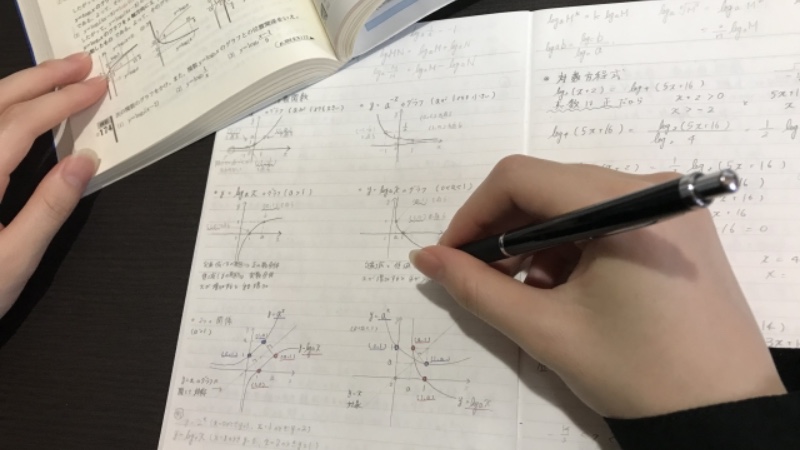
それでは次に、過去問を使った具体的な勉強方法について解説をしていきます。
勉強方法についても3つのポイントを押さえていきましょう。
勉強方法① 時間を計って実践演習
1つ目は実践力アップのために必ず時間を計って演習をします。
時間を計って演習することで、「どの問題にどれくらい時間がかかるか」を把握でき、先ほどの活用③「戦略を立てる」につながります。
短時間で確実に得点できる問題はどれか、逆に時間をロスしてしまう問題はどれかを知ることができます。


本番さながらで解くことが大切なんですね。
できれば、自分の試験時間と同じ時間帯での演習をしましょう。
例えば、私の母校の入試では、国語と外国語の2科目の試験があり、国語(12:30〜14:30)、外国語(15:20〜17:20)という時間設定です。
実際の入試の時間に合わせて問題を解きましょう。
目的は、もちろんターゲットとなる試験時間に集中できるように体を合わせておくためです。
間違っても、夜中に演習をしないようにしましょう!


勉強方法② 解き直しは2段階で時間をかける
問題を解いたら、自己添削と解き直しをする習慣を身に付けましょう。
解き直しは問題演習の基本だけど、解き直しは2段階でやっていこう。




2段階ってどういうことですか?
問題演習の具体的な手順を説明しますので、解き直しのタイミングを確認しましょう。
- 時間を計って問題を解く。
- 解答を見て自己添削をする。
- 解説は見ずに間違った問題を時間無制限でもう一度解く。
- すべての問題を解説を見ながら答えを確認する。
- 間違った問題をさらにもう一度解く。
ポイントは、最初の自己添削の時に、解説は読まずに間違った問題にもう一度チャレンジすること。このときは、時間を気にせず、たっぷりと時間をかけてもう一度考えることが大切。これが最初の解き直しになります。
さらに、解説を読んですべての問題の確認をした後で、もう1度間違った問題を解いて、解答にたどり着けるかチェックします。これが2回目の解き直しになりますね。
間違った問題については、自分の中での弱点になり得るので、ダブルチェックで潰していくようにしましょう。


間違った問題はしつこいくらい解き直すんですね。
勉強方法③ 繰り返し解く
最後のポイントは、すべての勉強に共通していること。
同じことを繰り返す。
過去問は最低5年分と言ったが、5年分を一度解いて終わりではいけない!


問題を1回解いたくらいでは、問題形式や傾向も頭に入ってこないし、戦略も身につかない。
5年分の過去問を最低3回は繰り返し解く。


15年分ですか!!
これくらいしつこく問題演習をすることで、志望大学の問いの傾向や狙い、対策が自分の中に入ってきます。
頭で分かっているだけでなくて、体で覚えているという状態にしたい!そのためにも最低3回は繰り返して欲しい!


「問題はもちろん、解説も覚えた」というレベルが目標です。
そこまでやり込んで始めて過去問を使って勉強したと言えます。


そこまで過去問をやり込んだら、傾向も対策もバッチリな気がします!
過去問の勉強方法3つのポイントをまとめます。
過去問の勉強方法まとめ
- 時間を計って演習する
- 解き直しはたっぷり時間をかけて2回解く
- 5年間分を最低3回は繰り返し解く
大学入試の過去問活用のまとめ
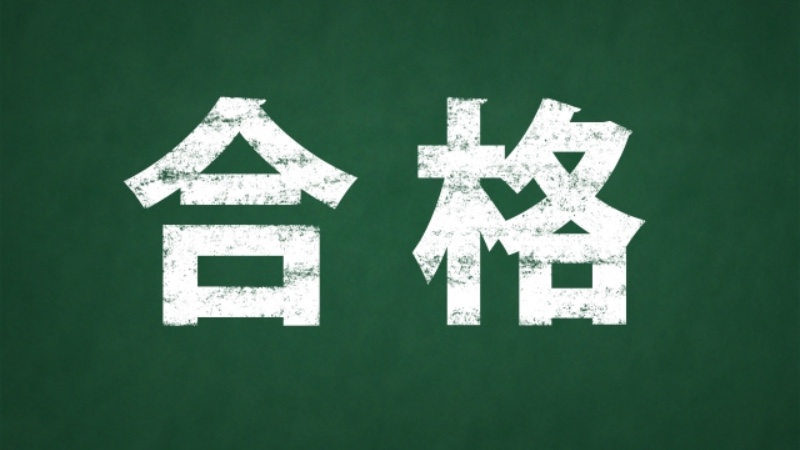
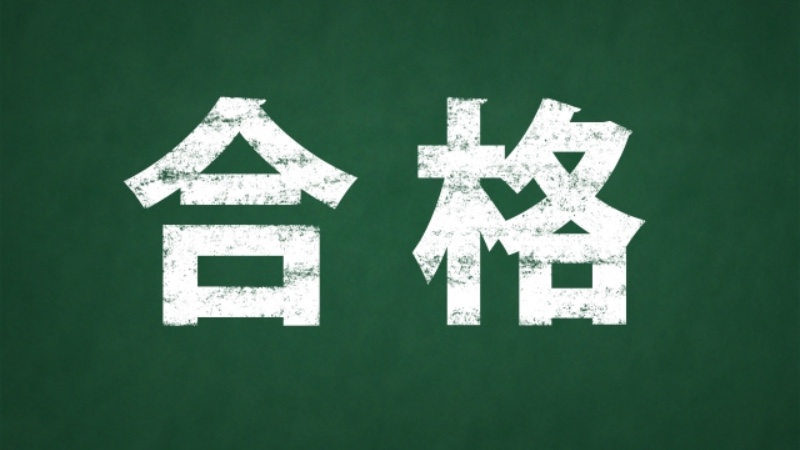
今回は大学入試の過去問を活用方法と過去問を利用した具体的な勉強方法について解説しました。
志望校の過去問題集を手にしてはいる受験生は多いけど、実際に活用できている受験生はほんの少数です。
過去問をやったら必ず合格するわけではありませんが、過去問を徹底的に活用して勉強することで、合格に大きく近づきます。
過去問演習のやり方に悩む受験生の参考になれば幸いです。
受験までもう一踏ん張りです。
諦めずに勉強していきましょうね。
最後までお読みいただきありがとうございました。