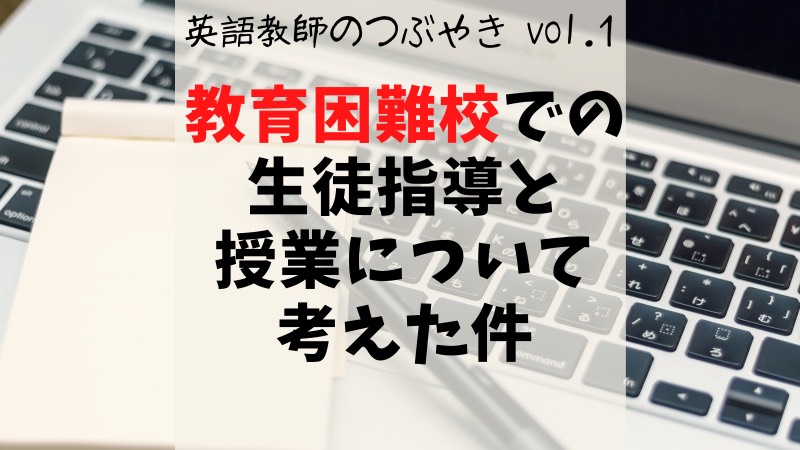この記事について
英語や授業、日々のことについて、なんとなく書いていく日記的な内容です。
今回のテーマは「教育困難校」での授業について。
教育困難校での授業は、教員であれば、誰もが経験したくないけど、経験してしまうという罠。
いわゆるしんどい学校での立ち回り、特に生徒指導(生活指導)と教科指導(授業)について考えます。
悩める教育困難校の教師のお役に立てば幸いです。
[toc]
教育困難校は何が困難なのか

いわゆる教育困難校。何が困難なのか。
困難なポイントは大きくは2つ。
- 基本的に生徒は言うことを聞かない
- 生徒の学力が低い
要は、言うことを聞かない生徒、勉強ができない生徒、この2つの要素が困難の根本になりますが、正直言って、教師が辛さを感じるのは、学力の低さよりも、言うことを聞かない、指導に従わない生徒への対応でしょうね。
不思議なことに、指導に従わない生徒の保護者も指導に従わないケースが多いですが、保護者対応については、またの機会に書きます。
まずは、指導に従わない生徒への対応(生徒指導)について考えていきましょう。
教育困難校での生徒指導のコツ

教育困難校で教える中で、ここ(困難校)での生徒指導はとてもとても難しい。と肌で感じました。
最初は、生徒は言うことは聞かないし、授業もグダグダ。それでも、なんとかある程度は生徒が言うことを聞いてくれるし、授業も成立するようにはなりました。
困難校で過ごすうちの生徒対応のコツ?のようなものが少しだけ見えてきたからかな?と考えています。
教育困難校の生徒対応が難しい理由
さて、生徒対応が難しいなぁと感じる理由。あくまでも私の個人的な見解ですが、次の3つかなと思います。
- 教師に対する不信感
- 保護者の協力があまりない
- 理屈よりも感情が先にきてしまう
これら3つが思い当たったことですね。
これまでのいわゆる普通の学校では、あまり意識したことがありませんでした。
教育困難校の生徒は、基本的に教師に敵対心を持っているし、保護者は非協力的だし、理屈が通じないことが多い。
こう言ったことを踏まえて、生徒への対応を少し変えていくことにしました。
教育困難校の生徒に対応するポイント
上の3つの理由を踏まえて、次の3つのことを基本として生徒に対応していくことにしました。
- 不公平な指導はしない
- 叱りつけず冷静に話をする
- 出来ている事は認める
この2点だけです。当たり前のことかもしれないですが、意外に難しいんですね。
教育困難校にいるような、教師に反抗的な生徒は、基本的に大人の指導に対して不信感を持っています。
そういう生徒の口ぐせ(?)は、「なんで俺らばっかり!!」
だから、それを言わせないために、誰に対しても同じような指導をしていかないといけないですね。
みんなに対して同じように指導をしています!と胸を張って言えるようにしておくと、意外に相手も納得はしてくれます。
そして、頭から叱りつけない。
困難校の生徒は、理屈より感情が先に立ってしまうから、「怒られた」が残ってしまって、そこで思考が止まってしまいます。もう話が通じません。
対応するこっち(教師側)も人間だから腹が立つけど、冷静に話します。
例えば、何か指導にかかるような行動をしたとしても、いきなり「コラー」と叱るよりも、きっちりと落ち着いて話すほうがいいですね。
- 何がいけないのか
- なぜそうなったのかの気持ちを聞く
- 気持ちはわかるけど、ダメなものはダメ
これだけで、意外に生徒は素直に話をしてくれるし、ある程度指導を受け入れてくれます。
さらに全部ダメ!ではなくて、出来ている事は認めてあげることも大切。
全否定してしまうと、本当に不信感しかもたないから、良いところ、出来ているところは認めることも必要ですね。
もっとも、「公平な指導・冷静に話す・認める」という3つのポイントは、教育困難校だけではなく、すべての学校の生徒にも通じることだと思います。
私自身、いわゆる進学校での経験が長かったので、感情的に生徒を頭から叱りつけることも多かったですね。だからこそ、教育困難校では苦労したのですが。
教育困難校での教科指導
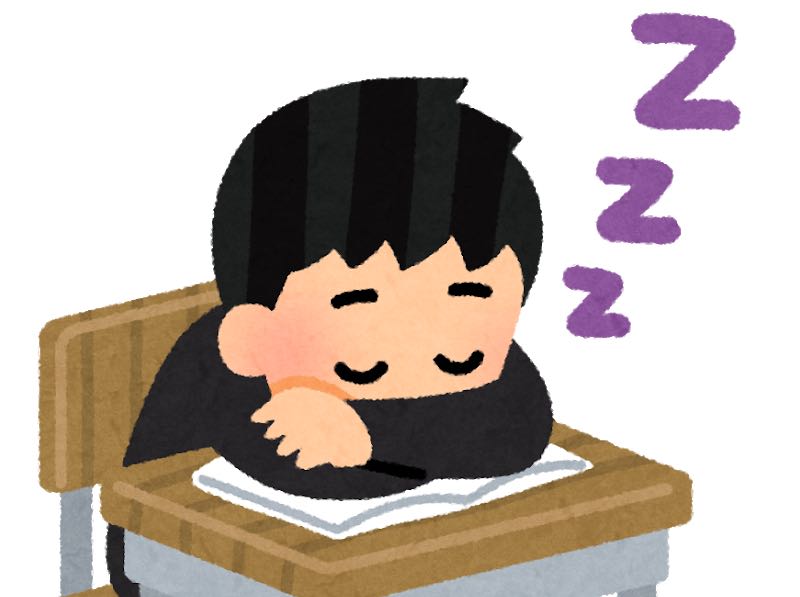
次は、教育困難校での授業について考えていきましょう。
こういう学校で教師が理解しないといけない事は・・・
- 学力が圧倒的に低い生徒と普通の生徒が混在
- 基本的に勉強が嫌いで意欲が低い
だから、普通に授業をしても基本成立しない。
正直、受験もしないので、学力を上げる必要性もない。
ぶっちゃけていうと、困難校での授業は「どうやって50分もたせるか」ということになります。
普通に授業をしても、授業崩壊にしかならないので、低レベルであっても、授業っぽくするために、授業を変えていきました。
それは次の2つだけ。
- 映像を入れる
- ゲーム要素を入れる
結構、当たり前のことですが、意外に食い付きがよくなります。
進学校の授業では、生徒は授業を聞いて当たり前、でも、困難校ではそうはいきません。なんとか、授業にするためには工夫が入りますね。
授業に映像を入れる
英語の授業で「テリーフォックス」についてのレッスンがありました。
テリーフォックスさんは、カナダの方で、片足義足でマラソンしたという伝説的な人物。しかし、ただ英文を読むだけでは、生徒は食い付かないので、Youtubeでテリーフォックスに関する動画を探したり、パラアスリートの動画を探したり、と関連する映像を探しては、生徒に見せて、ちょっとでも教材内容に興味を持つように仕向けます。
映像を見せたからと言って、全員が食いつくわけではないですが、ゼロではないかな?と思いました。
多少でも、興味を持ってくれるし、英文を読む際の予備知識になったので、ある程度、良い効果があったと考えます。
ゲーム要素を入れる
次にやるのはゲーム的な要素を入れること。
私はよく授業の「つかみ」としてやっています。例えば、授業最初の5分くらいを使って英語のパズルを解かせる。
クロスワードパズルはある程度、英語力が必要なので、おすすめなのは「ナンクロ」。
英単語ナンクロは、英語の知識よりもパズルの要素が強いので、学力が低い生徒でも取り組めるし、逆に英語がまったくできない生徒の方ができることもあって、意外に盛り上がります。
私がよく使っているのは『中学英語でできる!英単語ナンクロ』
出てくる単語のレベルも低いし、ヒントも付いているので、とても取り組みやすいですよ。
まとめ 教育困難校での仕事は経験になる
教育困難校に転勤が決まった時は、ガチで凹みました。
今でも早く転勤したいですが、教育困難校での仕事はかなりの経験になりました。
生徒への対応の方法や授業の方法について改めて考えるきっかけになったのかな?と思います。
いわゆる普通の学校にはいないような、色んな事情を抱える生徒や保護者との対応で、ちょっとは教師として進化できているのかもしれませんね。
この記事が、同じような困難校の教師の方の参考になれば幸いです。